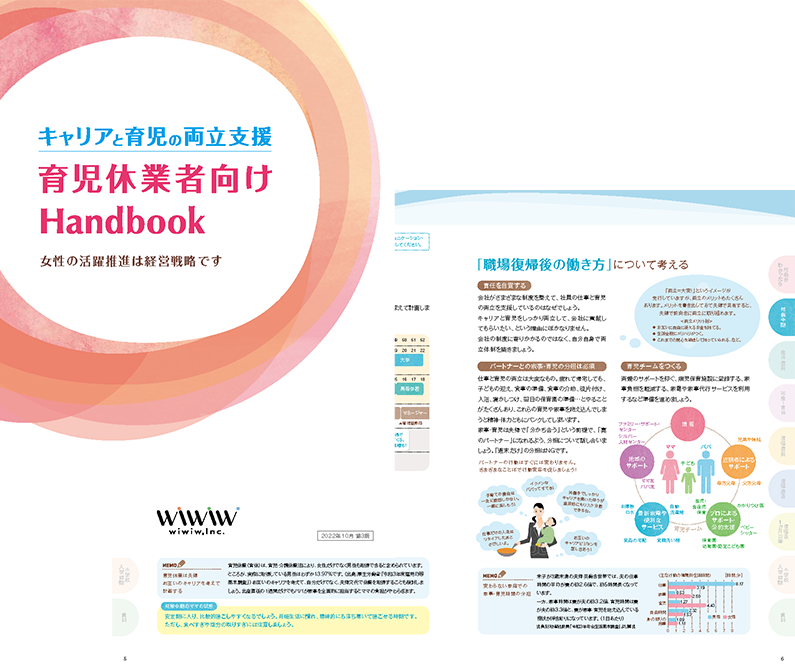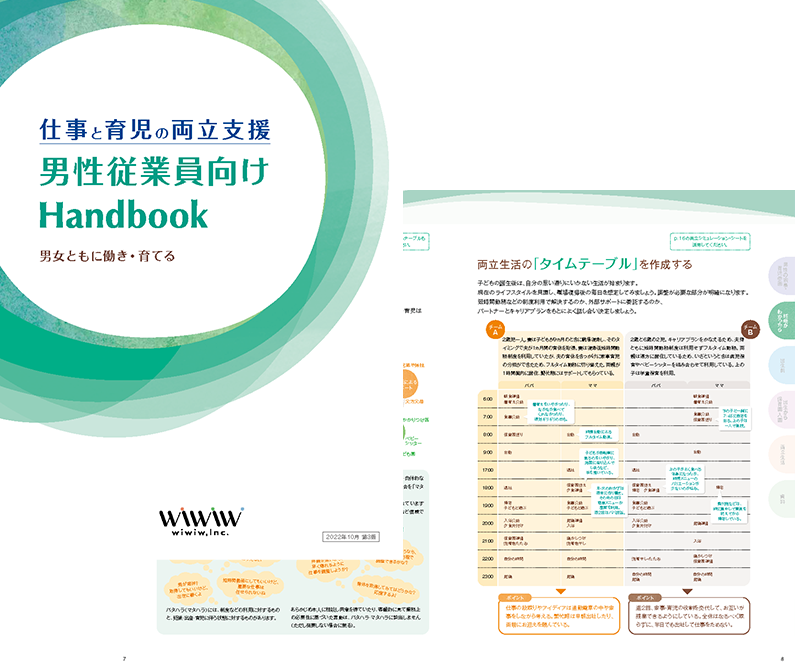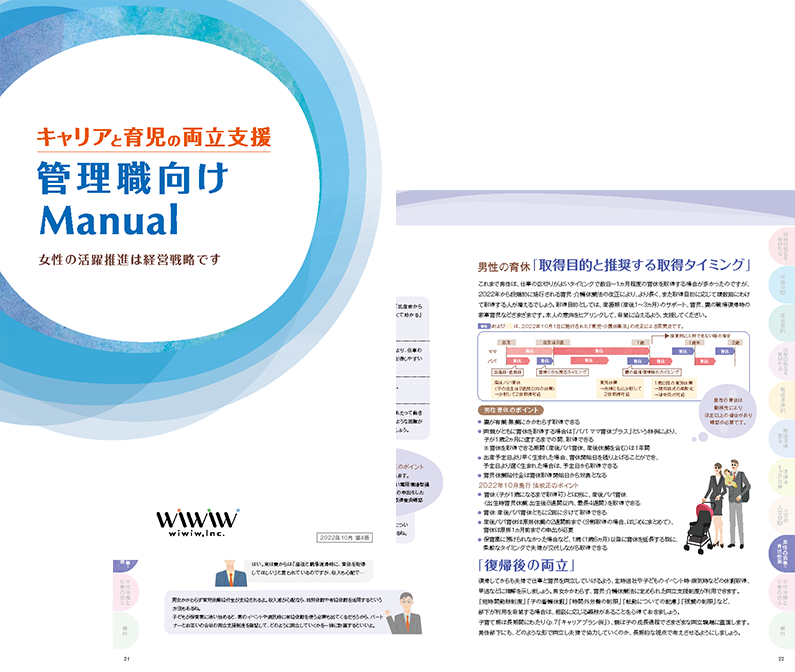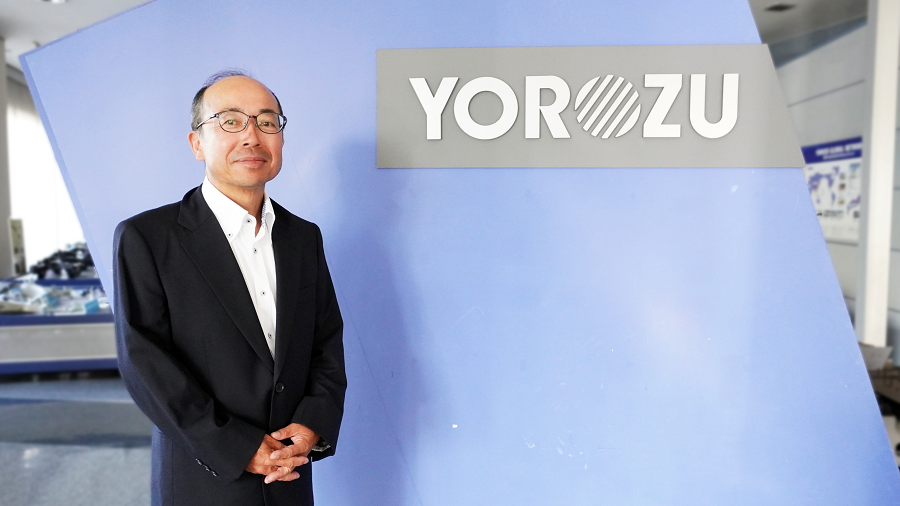wiwiw企業インタビュー
株式会社東海理化(株式会社東海理化電機製作所)様
人事部 部長兼 ダイバーシティ推進室 主査
熊田 康男 様
人事部 働きがい改革推進室
髙橋 聡子 様
本社工場 大口部品生産部 ワーキンググループ
班長
内藤 友美子 様
リーダー
岡 柊斗 様
株式会社東海理化様は主に自動車用各種スイッチやシフトレバーなどのHMI(ヒューマン マシン
インタフェース)製品、スマートエントリーシステムをはじめとしたセキュリティ製品、シートベルトを中心としたセイフティ製品などの開発・製造を行っており、人とクルマの接点を支える技術を追求し続けてこられました。変化の激しい自動車業界において「人を大切にすること」を経営の中心に据え、多様な人材が活躍できる企業風土の構築に力を入れていらっしゃいます。
ダイバーシティ推進のお取り組みとキャリアと育児の両立支援BOOKの導入とともに実施した施策について伺いました。
「全員活躍を実現するチームづくり」 ― 社員の意欲・働きがい向上に向けて

貴社の経営戦略におけるダイバーシティ推進の位置づけについて教えてください。
熊田様 東海理化では、社員が働く幸せや働きがいを感じられる環境を整備し、仲間と共に意欲高く仕事に取り組み、能力を発揮することで企業の持続的成長を実現することを目的に、D&Iを推進しています。自動車業界も例外ではないVUCAの時代において、社員全員の活躍、一人ひとりが持っている能力を最大限発揮することが、多様化するお客様のニーズをキャッチしお客様に喜んでいただける技術、製品をお届けすることにつながると考えています。
D&I推進を加速するきっかけや、取り組みについて教えてください。
熊田様
2021年にトップによるダイバーシティ宣言を発表し、翌2022年にはエグゼクティブオフィス直轄のダイバーシティ推進室を新設しました。制度設計や採用、人材育成を担う人事部と連携しながら、D&Iの推進に戦略的に取り組んでいます。
現在は、上司層を対象にしたダイバーシティマネジメント教育の実施や、社員が多様な知や経験を得て、より高い視座と広い視野をもって仕事に向き合えるよう、異業種他社との交流機会の創出にも力を入れています。こうした取り組みを通じて、社員の経験や価値観といった”内面の多様性”にも着目した、タスク型ダイバーシティの推進も見据えた取り組みを進めています。

社員全員の活躍に向けて、両立支援についてはどのように捉えていらっしゃいますか。
髙橋様
「全ての社員が仕事とそれ以外の時間を両立しながら人生を歩んでいる」という考えのもと、2024年2月より両立支援の対象を、育児・介護・治療期の社員に限らず、「全ての社員」へと拡大しました。具体的には、社外副業制度や勤務間インターバル制度の導入などに取り組み、社員が、仕事とそれ以外の時間を自分で調整しながら、価値観やライフイベントを尊重した働き方ができるようサポートしています。
一方で、育児・介護・治療期には、時間や他者の制約を受けるため、「これまでと同じ働き方」が難しくなり、「新しい働き方の模索」が必要になります。
東海理化ではこの時期を「チャレンジ精神を育む機会」「成長の機会」と捉え、特に手厚い支援を行っています。こうした取り組みが、社員の前向きな意欲を引き出し、働きがいの向上と、会社の成長につながると考えています。
現場から始まる職場変革とお互い様の風土醸成 ― ワーキンググループの活動
ダイバーシティ推進に取り組むにあたっての工夫を教えてください。
高橋様
東海理化では、生産現場の声に耳を傾けながら、人事(事技部門)と生産部門が両輪となってダバーシティ推進に取り組むことを大切にしています。
なかでも大口部品生産部は、自職場の自主的な取り組みとして、いち早くダイバーシティ推進を開始しました。ワーキンググループを立ち上げ、職場のコミュニケーションや居心地の良さといった視点から環境整備を進めるほか、女性や年長者が作業しやすい工夫、下肢障がいのある方も安全・安心に作業できる「車いすライン」の構築など、現場発で多様性への配慮を実践しています。
同部の取り組みに刺激を受け、現在では本社工場、豊田工場、音羽工場など、各工場・各生産部門でも多様な自主活動が展開されています。製造業の要である工場が主体的に工場発意の施策を展開していることは、当社のダイバーシティ推進における大きな特長の一つです。

ワーキンググループの活動はどのようにして始まり、広がっていったのでしょうか。
内藤様 ダイバーシティ推進に関する会社の方針が示された当時、私が所属する生産現場では女性社員の比率がわずか6%でした。そんな中、「女性も活躍できる職場であることを知ってほしい」「もっと働きやすい職場をつくりたい」という女性社員の声をきっかけに、活動がスタートしました。初期は手上げ制でメンバーを募り、「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージを払拭するため、現場改善や作業環境の工夫に取り組みました。通常業務とは別の活動であったため、当初はなかなか理解が得られない時期もありましたが、管理職を巻き込み協力を得ることで、性別や年齢、ハンディキャップの有無にかかわらず、多様な方に参加してもらえるようになり、より良い職場づくりへと発展していきました。
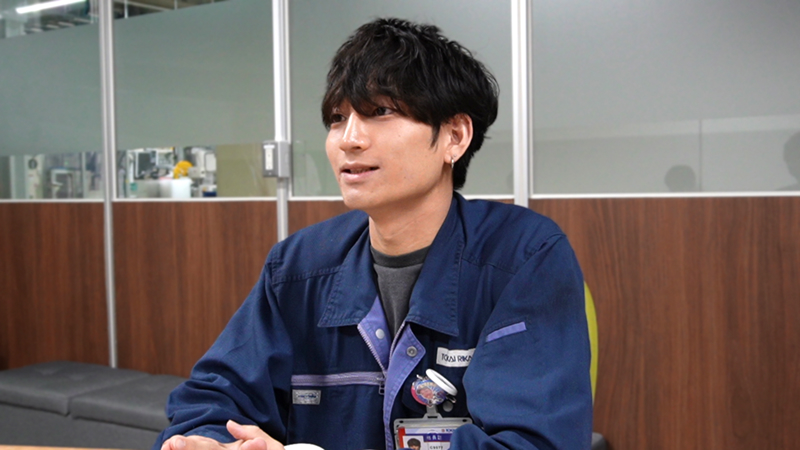
岡様
私は上司から声をかけていただき、ワーキンググループに参加しました。その後、リーダー交代のタイミングで自ら立候補し、リーダーを務めることになりました。
ワーキンググループでは、1つの課題に対して2~6ヵ月単位で改善に取り組み、進捗や気づきを他の社員と共有する場を定期的に設けています。活動を通じて制度に詳しくなった社員が、次の対象者を支える、といった好循環も生まれています。
この活動そのものが、現場のコミュニケーションを活性化し、「お互い様」の風土づくりにもつながると考えて、日々活動をしています。
熊田様 こうした現場発の取り組みをさらに広げていくために、ダイバーシティ推進室では、ワーキンググループのメンバーへのインタビューを実施し、その内容を記事や動画にして社内ホームページで発信しました。この情報発信をきっかけに、活動に興味・関心を持つ社員が増え、他部門や他工場にも取り組みが広がっていきました。
両立支援は「弱者支援」ではない ― 制度と意識を変える取り組み
育児期の社員への支援を検討するにあたり、当初の課題をお聞かせください。
高橋様それぞれ次のような課題を感じていました。
-
①若手社員
ライフイベントを踏まえたキャリア形成支援が不足しており、中長期的なキャリアデザインが描きづらい。その結果、女性のキャリアアップや男性の育児休職取得・家事育児参画につながらない。
-
②育休者
同僚に負担がかかることへの罪悪感から育休取得にブレーキがかかる。 育休期間が育児に専念する期間となり、両立体制の構築や復職への心構えが不十分なまま職場復職を迎えている。
-
③上司
育児期の部下に対するキャリア支援法や考え方が分からず、ハラスメントへの不安から、プライベートにどこまで踏み込んでよいか判断が難しい。
そうした課題がある中で、当社のキャリアと育児の両立支援BOOK(以下、ハンドブック)を導入いただいた理由を教えてください。
熊田様 まずは会社全体で分かりやすい共通認識をつくる第一歩を踏み出したいと考えていました。今ライフスタイルを考える人も、これから考える人も、支援する立場の人も、誰もが手に取れる内容であることを重視しました。中でもwiwiwのハンドブックは、“男女ともにキャリア形成をする”という視点が盛り込まれており、対象者やフェーズごとの対応事項やポイントについて共通認識化が図れる点が特に良かったです。
高橋様 両立支援が「弱者救済」と捉えられると、制約のある働き方をする社員をフォローする側に不満が生じ、働き方改革が進みにくくなります。しかし、組織の10年先を見据えると、制約のある働き方をする社員は確実に増えていきます。これからは、誰もが働く人生の中で、制約がある時期・ない時期を波のように繰り返し、仕事とそれ以外の時間を両立していく時代になります。フォローしてもらう時期も、フォローできる時期もあるのだから、長い目でみたお互い様として「ポジティブな助け合い」ができる組織風土が必要だと考えました。そのために、両立支援は「全ての社員が充実した人生を歩むために必要なとりくみ」という捉え方を、組織の大事なメッセージとしてハンドブックに盛り込んで発信しようと考えました。
ハンドブックの制作にあたっては、大口部品生産部の方々にも協力いただきました。
高橋様 生産現場の社員にとっても違和感のない内容か、紙と電子どちらで展開すべきか、面談の仕組みが現場で運用可能かなど、管理職・男性育休取得者・ワーキンググループと何度も意見交換し、その声を反映しました。
内藤様 ワーキンググループのメンバー以外にも、希望者は誰でも意見交換に参加できるように声掛けしました。育休取得を躊躇していた人も情報交換できたり、日々の活動を職場へ共有できる雰囲気ができたりして、とても良い機会になりました。この経験は仕事にもプラスになっているので、今後も拡大していきたいです。
ハンドブックの導入とあわせて、妊娠から復職までのサポートを仕組み化されたと伺いました。詳しくお聞かせください。
熊田様2024年2月より、妊娠が判明した段階から復職1ヶ月後までをサポートする一連の体制を整備しました。
-
①育休取得や育児との両立に対する意識改革
「会社に迷惑をかけてしまう」というマイナスの意識から、「新しい事への挑戦の機会」「成長の機会」であり、組織の成長にもつながるというプラスの意識へ変わるよう定義。
-
②「早期の妊娠報告」と「妊娠から復職までの面談の仕組み」の導入
- 早期に妊娠報告をしてもらうことで、職場の人や仕事の調整を早めに開始。
- フェーズごとに面談を実施し、両立期のキャリア形成支援を行う。
-
③仕事と育児の両立支援説明会
- 室課長・直属上司・妊娠を報告した社員(男女)の3者で参加する説明会を毎月開催。
- 妊娠報告後、タイムリーに上司部下が共に人事から説明を受けることで、ダイバーシティ推進の本質と、ライフイベントを踏まえたキャリア形成の重要性を、自分事として受け止めてもらえるよう支援。
-
④トップからのメッセージ動画配信
社員向けと管理職向けに動画配信し、妊娠報告・育休取得・仕事と育児の両立を躊躇していた男性社員と管理職層の背中を後押し。
これらの取り組みでは、ダイバーシティ推進の意義、両立支援は弱者救済ではないこと、自組織の改革・キャリア形成支援の必要性など、会社の方針をしっかりと伝えることを重要視しました。
また、ハンドブックを参考にして「早期の妊娠報告」と「妊娠から復職までの面談」を仕組み化しました。妊娠報告はシステム化しており、対象者が申請すると直属の上司にメールが送られます。その後、直属の上司が必ず妊娠初期の面談を実施し、個別周知として資料を配布したうえで、
育休取得の意向確認をします。育休取得者には、パートナーと一緒にハンドブックを読んでもらい、パートナーと子育てや今後の働き方について話し合う時間をつくっていただいています。ハンドブックは電子書籍として提供しており、自宅でも閲覧できるため、社員からも好評です。
育休前に3回の面談を実施し、育休の取得期間を決定します。復職前後にも3回の面談を行い、状況に合わせた支援を継続しています。

仕事と育児の両立支援説明会
ハンドブックを導入してご満足いただけた点や成果について教えてください。
高橋様
ハンドブック導入を含めた一連の取り組みを開始して1年間で、両立支援説明会後のアンケートの内容が大きく変化しました。
上司からは、「代替要員を入れるだけでなく、組織全体の働き方を見直すことが大事だと気付いた」「数年後は自分も病気や介護に直面する可能性があると考えるようになり、今の働き方でよいのか自問自答するようになった」という声が寄せられています。
また、男性育休取得者からは、「会社が育休取得をマイナスではなくプラスのこととして捉えていると感じた」「今後管理職になったときに、育休の経験が役立つスキルにつながると思った」といった前向きな声が多く届いています。
仕事と育児の両立支援説明会を毎月開催することは、運営側にとって負荷もありますが、タイムリーに、地道に実施を続けることで、対象者だけでなく、“職場全体にとっての両立支援”という雰囲気が徐々に広がっていると感じています。
また、男性社員の育休取得率は、2021年度の22.6%から2024年度には91.4%と劇的に向上しました。
継続的な課題と、今後の取り組みについて
今後の取り組みについてお聞かせください。
高橋様
これまでの取り組みを振り返って、現在の課題は主に次の3つです。
- 1.両立支援説明会の参加対象でない社員
- 2.男性の家事・育児参画を前提とした働き方の見直し
- 3.若年層のキャリア形成意識の醸成
組織全体としてお互い様の風土を醸成すること、現場の働き方改革、性別役割分担意識の改革など、これらの課題はすぐに解決できるものではありませんが、「改めて、この会社で働かせて頂きたい、長くお休みさせて頂いた分を恩返し出来ると良いなと思いました」と言ってくれる社員も出てくるようになりましたので、今後も仕組みと風土の両面から継続的に取り組んでいきたいです。