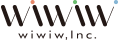wiwiw介護アドバイザーの角田です。
要介護認定で、要支援や要介護と認定されると、介護保険サービスを利用することができます。
そのサービスの値段が、4月から変わります。
一つひとつのサービスの値段は、介護報酬といって、厚生労働省が定めています。介護報酬は、3年ごとに見直すことになっていて、ちょうど2018年4月が改定月に当たります。
要介護1~5の人を対象にした 30分以上1時間未満の訪問介護(身体介護)は、これまでは388単位でしたが、4月からは394単位になります。6単位の値上げです。
ここで、「単位って何?」と思った方も多いでしょう。
その説明をする前に、皆さんは、最低賃金制度をご存知ですか。
使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額(1時間当たり)を定めた制度で、一番高いのは東京都の958円、一番低いのは、福岡県以外の九州6県と沖縄県の737円です。
221円もの差がついているのは、東京は家賃や物価が高いので、そのくらい多くもらわなければ、同じレベルの生活はできないと考えられているからです。
つまり、人件費は、全国一律ではなく、地域によって異なります。
要介護度は、高齢者が日常生活を送るのにどのくらい「介護の手間」を必要とするかに基づいて決められます。介護サービスを「介護の手間」と考えると、介護サービス費は手間賃、つまり人件費の割合が高くなります。
そこで、国は、個別の介護報酬に、そのサービスにどのくらい人件費がかかるかと、地域ごとの人件費を反映させることにしました。
先ほどの訪問介護の人件費割合は70%で、訪問リハビリは55%、ショートステイは45%と、人件費割合は3区分になっています。
地域差は、最低賃金のように都道府県単位ではなく、介護保険の運営者が市区町村であるのに合わせて、市区町村単位になっています。
全国の市区町村を公務員(国家・地方)の人件費に基づいて、1~7級地とその他の8つの区分に分けました。
1級地は東京23区で、20%上乗せ。
2級地は東京都狛江市と多摩市と町田市、神奈川県横浜市と川崎市、大阪府大阪市で、16%上乗せ。
3級地は埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、東京都の13市、神奈川県鎌倉市、愛知県名古屋市、大阪府の4市、兵庫県西宮と芦屋市と宝塚市で、15%上乗せ。
4、5、6、7、と上乗せ割合が減って、その他は上乗せはありません。
平成30年度からの地域区分表を見れば、親御さんの住所地が、どの区分に属しているかがわかります。東京都町田市は3級地から2級地に、さいたま市は4級地から3級地に、今回の改定で変わりました。
ようやく単位の説明になりますが、介護報酬は、全国一律で、金額ではなく単位で表されます。先ほどの訪問介護(身体介護)を例にとると、4月からは394単位なので、その他の地域は、394単位に上乗せ無しの10円をかけて、394単位×10円=3,940円ということです。
1級地である東京23区では、人件費割合70%×地域区分20%=0.14を基本単位10円にかけて、1.4円が上乗せになります。
394単位×(10円+1.4円)=4,491.6円。小数点以下は切り捨てになるので、東京23区では4,491円になります。
利用者は、この1割か2割を自己負担します。
今回は、頭が痛くなるような話になってしまいましたが、要するに、4月から介護サービス費が変わることと、介護サービス費は全国一律ではないことをご理解いただければと思って取り上げました。
それから、介護報酬はケアマネジャーが計算してくれますので、ご心配はいりません。計算ソフトが普及しているので、ケアマネジャーが自分で電卓で計算するということはないようです。
介護保険は本当に複雑な制度ですね・・・
つのちゃん
最新記事 by つのちゃん (全て見る)
- 75歳になると、認知機能検査に合格しないと運転免許更新はできません - 2025.07.03
- 出生数減少は介護の危機を招く - 2025.06.10
- 介護休業制度改正をわかりやすく解説します - 2025.04.28