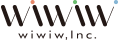介護アドバイザーの角田です。
「老親の介護は家族の責任」とされた時代から、「介護は社会で担うもの、介護サービスを利用して行うもの」に大きく変わったきっかけは、1997年の介護保険法の公布でした。
日本の介護はどうなるか、その将来像を正確に予測することは難しかったため、3年ごとに法律を改正する仕組みが導入されました。介護保険法が「走りながら考える」法律と呼ばれる所以です。
2021年はちょうど改正の年に当たります。
今回は、2021年の介護保険法改正で変わることについてお伝えします。
①高額介護サービス費の上限額の引き上げ
高額介護サービス費とは、月単位の介護保険サービス費の自己負担額が上限を超えた場合、超過分の払い戻しを受けられる制度です。
これまで「本人または世帯全員が住民税課税者」であった場合、自己負担額の上限は一律4万4,400円でしたが、下表で色付けした区分の上限額が引き上げられます。
対象になった人には市区町村の介護保険課から申請書が届きますので、払い戻しの申請をしましょう。一度申請するとそれ以降は、負担限度額までの支払いで済むようになります。
| 対象者の区分 | 該当条件 | 自己負担の上限額(月額) |
| 本人または 世帯全員が住民税課税者 |
年収1,160万円以上 | 14万0,100円(世帯) |
| 年収770万円以上1,160万円未満 | 9万3,000円(世帯) | |
| 年収770万円未満 | 4万4,400円(世帯) | |
| 世帯全員が住民税非課税者 | 下記以外 | 2万4,600円(世帯) |
| 前年の合計所得金額と公的年金、収入額の合計が年間80万円以下 | 2万4,600円(世帯) 1万5,000円(個人) |
|
| 生活保護を受けている人 | 1万5,000円(個人) |
「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した人全員の負担の合計の上限額を指し「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。
②介護保険施設のホテルコストの負担軽減対象者の見直し
介護保険施設に入所したりショートステイを利用したりした場合、食費と居住費は、介護サービス費とは別に全額自己負担になります。
毎日負担する費用のため、施設の利用が難しくなるケースもあり、住民税非課税世帯の人を所得に応じて第1、第2、第3の3つの段階に区分して負担を軽減していました。
2021年の改正では、第3段階を2つに分け、補足給付の額も変更になります。
預貯金等の基準の見直しもあり非常に細かい改正のため、該当するかどうかは市区町村の介護保険窓口や施設に問い合わせましょう。
負担軽減制度を利用する場合は市区町村から「介護保険負担限度額認定証」を毎年発行してもらって施設に提示する必要があります。
①、②ともに、2021年8月以降、変更になります。
今回の改正では、「ケアマネジメントの有料化」「要介護1・2の方の生活援助の市区町村への移管」「保険料負担年齢の引き下げ」「利用者の自己負担の増額」などの検討事項は先送りになっています。
2021年は介護報酬も改定になります。介護報酬というのは介護サービスの値段のことで、利用者の自己負担額に大きくかかわってきます。次回は介護報酬改定について紹介します。
仕事と介護の両立に関する講演・研修・コンサルティングのご相談は、こちらまで。
つのちゃん
最新記事 by つのちゃん (全て見る)
- 出生数減少は介護の危機を招く - 2025.06.10
- 介護休業制度改正をわかりやすく解説します - 2025.04.28
- 高額介護サービス費を知っていますか - 2025.03.28